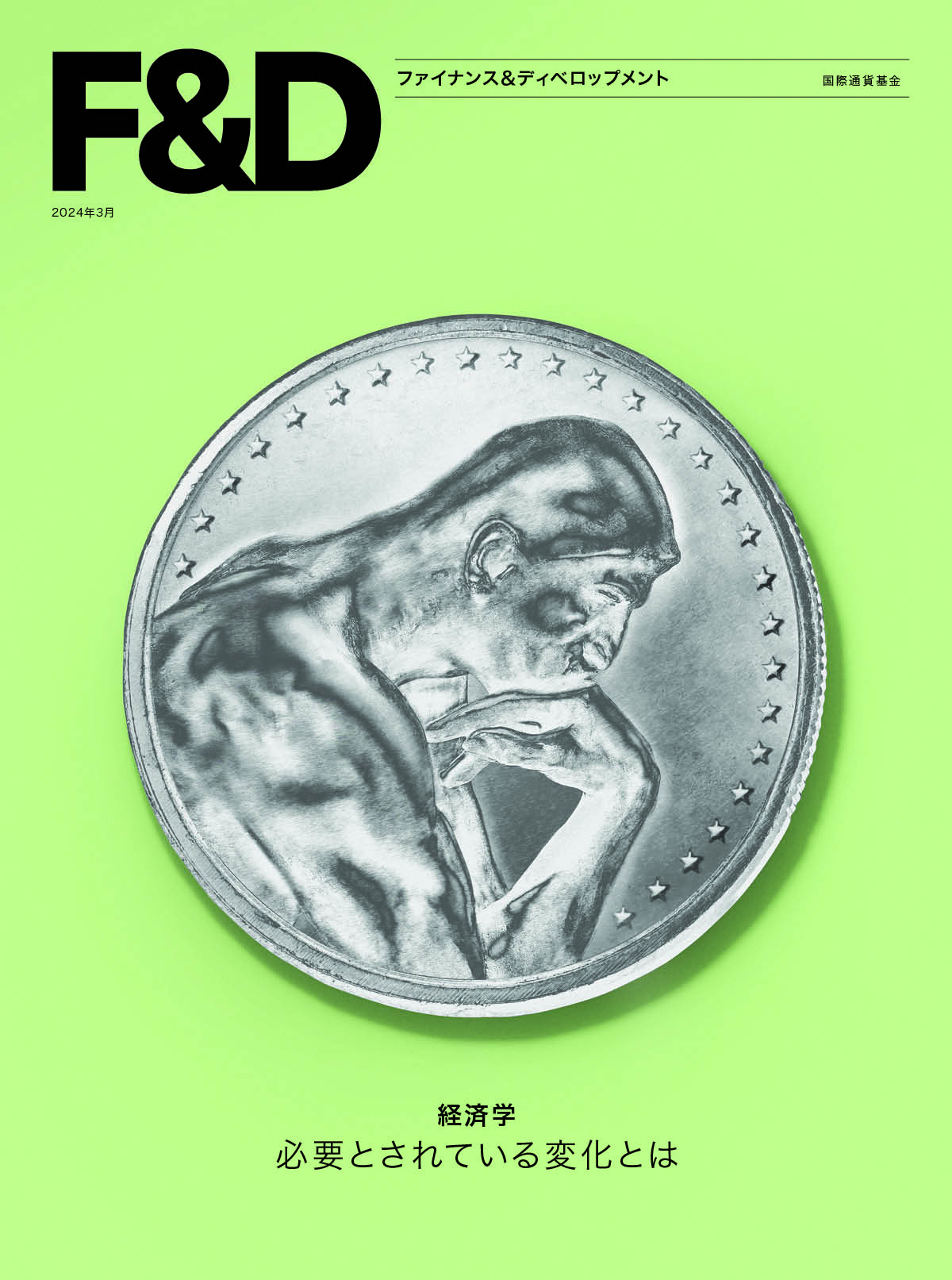金融政策の基盤・枠組みを再考する時が来た
エリザベス2世女王が2008年に、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の教授に世界的な金融危機について質問したことはよく知られている。「なぜ誰も予測できなかったのか」。チャールズ3世が今日、母親と同じ道をたどるとすれば、確実に似たような質問をするだろう。ただ今回は高インフレについてである。
これはいつになく差し迫った質問だ。その理由はふたつ。第1に、最近のインフレ率が40年ぶりの水準に急上昇する前は、先進国の多くの中央銀行は圧倒的に、低インフレの方を懸念していた。第2に、中銀当局者は自信を持ってインフレが一時的なものであると主張し、価格が急速に上昇したにもかかわらずインフレを抑制することができなかった。引き金となった出来事(特にパンデミックと、ウクライナでの戦争による貿易と生産の混乱)は、供給サイドに由来する。これらは金融政策の範疇に入らないと見なされていた。しかし、引き金となった出来事がインフレに与えた影響は、既存の金融情勢によって左右される。そして金融情勢は金融政策によって形成される。したがって、中央銀行が完全に非難を免れたわけではない。
女王がLSEの教授に質問をしたときと同じように、学者や中央銀行当局者が、現在の金融政策の枠組み、そしてより根本的には、その裏付けとなる知的モデルを、じっくり省みる時が来た。
根拠のない懸念
米連邦準備制度理事会のパウエル議長は2020年8月に、ジャクソンホール会議の講演でデフレと、金利が下がり切る(いわゆるゼロ金利制約)という従来の懸念をうまく表現した。「インフレ期待が目標の2%を下回れば、金利もそれに連れて低下する。その結果、景気後退時に雇用をあと押しするために金利を引き下げる余地が狭まり、利下げで経済を安定させる力が弱くなる。世界の他の主要国でこうしたマイナスの動向が展開するのを目撃して、一度このようなサイクルが始まると、それを克服することが極めて難しいことが分かった。同じことがここで起きないように、できることをしたい」。
これは、インフレ率の低下に応じたに果敢な金融緩和を正当化するため、中央銀行が展開する議論の中でも最も重要なポイントである。妥当な見解のように聞こえるのだが、それは事実によって裏付けられなければならない。そして、パウエル氏が明らかに日本を意味した「他の主要国」の経験は、この見解の妥当性に疑問を投げかける。
実際、日本は他のどの国よりずっと早くゼロ金利制約に到達した。しかし、これが政策上の深刻な制約であったのならば、日本の成長率はG7諸国よりも低かったはずだ。しかし、日本の一人当たりGDP成長率は、2000年(日本銀行の金利がゼロになり、日銀が非伝統的金融政策を開始した頃)から2012年(中央銀行のバランスシートが膨らみ始める直前)まで、G7平均と一致していた。日本の労働人口一人当たりのGDPの伸び率は同期間、G7の中で最も高かった。
2013年以降、中央銀行のバランスシートがGDP比30%から120%に拡大した時期に日本銀行が実施した「金融政策の大実験」もまた、多くを物語る。これはインフレ面では、わずかな影響しか持たなかった。そして成長面でも、影響は控えめであった。これは日本だけでなく、2008年以降、非伝統的政策を導入した他の多くの国でも同様であった。
非伝統的金融政策が決して効果をもたらさないということではない。タイミングによっては、非常に強力なツールとなり得る。その好例が、中央銀行が長期金利に影響を与えるために政策金利の道筋に関する見通しを市場に強く示すフォワードガイダンスである。景気が悪い場合、市場参加者は何れにせよ金利が低い水準にとどまると予想するため、フォワードガイダンスはあまり効果的ではないが、経済が予期せぬ需要や供給のショックに見舞われると、低金利を継続するというフォワードガイダンスは、突如、景気を過熱させインフレを引き起こす可能性がある。これは、現在起こっていることを部分的に説明しているだろう。
政治的な未熟さ
インフレ率が目標を上回ることを公然と許容する柔軟な平均インフレターゲットが広く導入されたことも、中央銀行が政策をより早期に引き締めることに失敗した一因だ。中央銀行当局者は、物価が目標を上回ることを容認すると決めたとき、先代の当局者が何年も前に同様の困難に遭遇したにもかかわらず、金融政策のパンチボウルを取り上げることの本質的な難しさを忘れていた。自問してみよう。民主主義社会で、選挙で選ばれていない中央銀行当局者が、インフレ的な財政支出計画のお陰で選出された政府や議員たちに、そのインフレ的な支出計画を切り詰めるように求めることができるだろうか。
おそらく、中央銀行は、1980年代半ばから20年ほど続いた着実な成長と安定したインフレの時期を指す「グレートモデレーション(超安定期)」に、単に楽をし過ぎたのだろう。この期間に独立した中央銀行が金融政策を成功させたという一般的な見解は、詰まるところ、幸運と偶然によるものだろう。世界経済は当初、発展途上国や旧社会主義国の世界市場経済への参入、情報技術の急速な進歩、比較的安定した地政学的環境など、供給サイドの良好な要因の恩恵を受けた。こうしたことにより、低インフレと比較的高い成長を両立することができた。中央銀行の仕事は、政治的な負託をあまり必要としなかった。
こうした平和な時代を経験した後、中央銀行の独立性が広く受け入れられるようになると、中央銀行は非伝統的金融政策を展開し始めた。政策は必要な時には、まずまず簡単に解消できるというやや甘い考えがあった。残念ながら、世界は変わった。供給サイドの良好な要因を助長した環境は、地政学的リスクの高まりやポピュリズムの台頭、パンデミックによるグローバルサプライチェーンの混乱など、さまざまな面から挑戦を受けている。中央銀行は現在、インフレと雇用のトレードオフに直面しており、政策の巻き戻しは極めて困難である。
枠組みの再考
中央銀行がインフレの波を見逃した理由を省みるとき、われわれはこれまで頼ってきた知的モデルを再考し、それに応じて金融政策の枠組みを更新しなければならない。考慮すべき3つの課題を挙げる。
第1に、デフレの危険性とゼロ金利制約に引き続き焦点を当てるべきかどうかを再評価する必要がある。これは、現在の引き締めサイクルをどこまで続けるかという決断を左右するため、早急に検討されなければならない。米国のインフレ率がピークを過ぎる兆しがあるため、一部のエコノミストはすでに、インフレターゲットを引き上げるとともに、デフレのリスクを冒さないように十分な安全マージンを維持するため、追加の引き締めの度合を和らげることを求めている。
私はこの見解には懐疑的である。仮に、より高いインフレターゲットとさらなる利下げ余地がある状態で世界金融危機に突入していたとしても、世界経済が大きく異なる方向に進むといったことはなかったであろう。私は、1970年代と1980年代初頭の米国の高インフレを終わらせたことで知られている米連邦準備制度理事会のボルカー元議長と同意見だ。「デフレは、金融システムの重大な崩壊によってもたらされる脅威である」。それはまさに1930年代に起きたことであり、2008年は、その瀬戸際まで行ったものの、実際には起こらなかった。主な違いは、金融システムの崩壊を防ぐための取り組みが2008年の方が効果的だったことである。
利下げ余地が拡大しても、金融の不均衡が債券によって煽られた資産バブルや金融危機として顕在化した場合、何の役にも立たない。したがって、中央銀行は、インフレや需給ギャップといったマクロ経済の動向だけに注目していてはならない。金融機関や金融市場で何が起きているかにも注意を払う必要があるのだ。
第2に、なぜ中央銀行が金融緩和の長期化に追い込まれたのか、その結果はどうだったのかを振り返らなければならない。その好例が日本であり、急速な高齢化と人口減少などの構造要因による成長の停滞が、景気循環の谷として誤解されていた。その結果、何十年にもわたり金融緩和が続いた。これは、金利の低下が自然利子率の低下に対する反応であると言うことではない。むしろ、金融政策が、より抜本的な改革を必要とする構造問題に対する手っ取り早い解決策と化してしまったのだ。
奇妙なことに、金融政策をめぐる議論は、金融緩和と引き締めが比較的短期間で交互にやってくることを前提としていることが多い。そうであるとすれば、金融緩和は需要サイドにのみ影響するという伝統的な見方が正当化されるだろう。しかし、金融緩和が10年以上という、より長い期間にわたって行われると、資源の配分ミスによる生産性の伸びへの悪影響が深刻化する。金融政策は、供給サイドへの考慮によって導かれるべきではないが、それを無視すべきでもない。
国による違い
最後に、各国が金融政策の枠組みを作り出す方法の違いに注意を向ける必要がある。たとえば、雇用慣行が異なることによって賃金の動きが異なり、それによってインフレの動きも異なってくる。日本では、消費者物価の上昇が加速しているが、他の先進国に比べてはるかに遅いペースである。これは主に「長期雇用」のユニークな慣行によるものである。日本では、特に大企業において、上司が何としてでも解雇を避けようとする暗黙の了解があり、労働者が保護されている。よって企業は、将来の成長に強い自信がない限り、恒久的に賃金を引き上げることに慎重になる。これが低いインフレにつながる。
グローバル化した経済においても、社会契約や経済的構造の違いは重要である。これは、ひとつの数値を全ての国に適用するインフレーションターゲット戦略の論拠を揺るがす。変動相場制に代わる良い選択肢を見出せない理由を忘れてはならない。各国が好むマクロ経済の状況は異なり、その結果生じる国家間の違いはそれらの国の通貨の上昇と下落に反映される。通貨のアンカー(そのようなものがもしあるとすれば)は、金融引き締めによってインフレを抑制し、最後の貸し手になるという中央銀行の確固たるコミットメントによってのみ確立することができるのであり、インフレ目標を設定するという単純な行為によって確立されるものではない。
インフレーションターゲット自体は、1970年代から1980年代初頭にかけての深刻なスタグフレーションを受けて生まれた画期的な対策だった。それが変更不能だと考える根拠はない。その限界が分かった今こそ、過去30年間頼みにしてきた知的基盤を再考し、金融政策の枠組みを刷新する時である。
記事やその他書物の見解は著者のものであり、必ずしもIMFの方針を反映しているとは限りません。